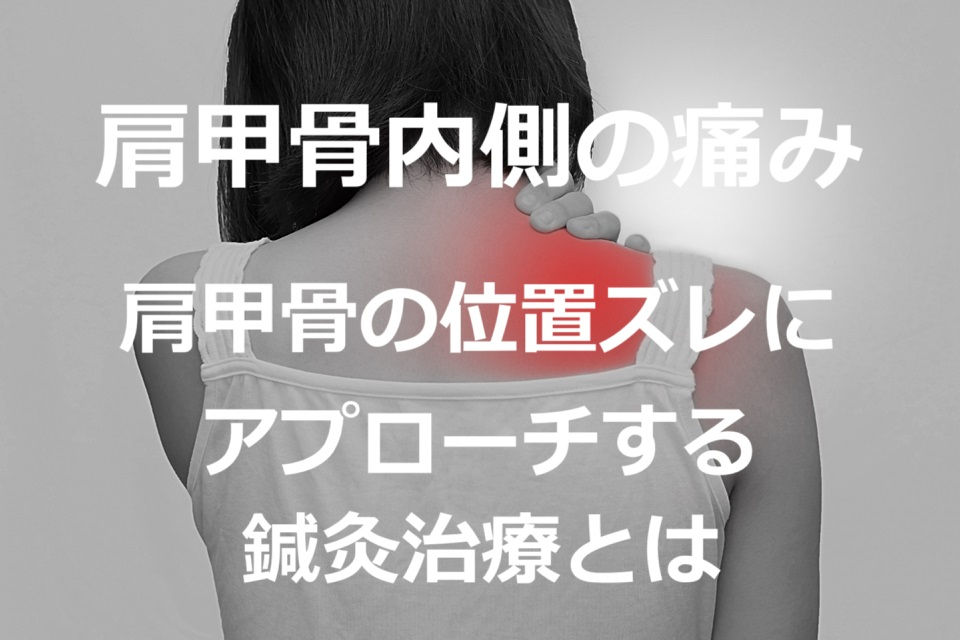力を抜くために知っておきたい たった1つのルール(五反田 鍼灸院)
- 加藤さやか

- 2020年9月25日
- 読了時間: 6分

先日、噛みしめ治療で来院されている30代女性のS様が、ふと、治療の合間の会話で、
実は4~5年前に初めて鍼灸院へ行くようになり、初めは胃腸の治療で通っていたこと。でも本当は、何年も前から”左右の肩の高さが違う”ことをお母様から指摘されて、ずっと気にしていたことをお話してくださいました。
鍼灸院に行ったのに、気になってる症状が言えない!?
初めて行かれた鍼灸院では、気にされている肩のことはお話にならなかったのですか?とお伺いしたところ、
胃腸の症状の方がツラかったこともあったし、他の症状を言ったらダメなんじゃないかと思って言えなかったんです・・・。そんな雰囲気じゃなかったし・・・。
と、かなり緊張されながら通われていらしたことをお話してくださいました。
力が抜けなくなるとき: 2つの理由
力が抜けなくなるのにはいくつか理由があるのですが、今回は2つの理由をご紹介します。
1. 脳ミソのメカニズムが力を抜きにくくしている?
鍼灸院やボディメンテナンス系の場所で、「力が入ってます!」「力を抜いてください!」って言われたことがある、という方は多いかもしれませんね。
「力を抜いて!」といわれても、意識的に力を入れてなければ、意識的に力を抜くことって、そもそも難しいんじゃないかな~って思うんですよね(;^ω^)
これって、緊張してる時に「緊張するな!」って言われても「ムリ~~~!(T_T)」ってなるのと似てるかも(笑)
実は、これ、脳ミソのメカニズムと関係があるそうなんです。
「力を抜いて!」という言葉を聞いた瞬間、脳ミソはその真の意味を探ろうとするそうです。
つまり、「力を抜いて!」とは、「あなたはチカラが入っている!」という真の意味を受け取ってしまうという脳の仕組みがあるため、からだはますます力を抜きにくくなるのだそうです!Σ(゚Д゚)
2. 自分の中のブレーキが 力を抜きにくくしている!?
今回のS様にはこちらの理由の方が、大きく関わっているものだったようです。
それは、
○○しちゃダメなのかな・・・。(気になる症状だけど言っちゃダメなのかな・・・)
○○しなくちゃダメなのかな・・・。(症状は1つずつ言わなくちゃダメなのかな・・・)
って、症状があるから鍼灸院へ通われていた(良くなるために前に進もうとしていた=アクセル)反面、他の症状を言ってはいけない(本当は気にしている症状を言えない=ブレーキ)と同時に思われていたことです。
当時のS様は、心の中にブレーキがたくさんあって、自由に思ったことを言葉にすることができず、心からリラックスできなくなってしまわれたのではないかと思います。
そりゃぁ、心の中が不安だったり、心配だったり、緊張だったりでいっぱいになってしまうので、力が抜けなくなってしまいますね!
力が抜けないことに悩まれていらっしゃる方は、力が抜けなくなるときのポイントをまずは押さえておくだけでも、「あぁ、自分せいじゃなくて脳ミソが勝手に変換して力が入ってるんだなぁ~」「あぁ、自分は今こんな風に感じてチカラが入ってんだな~」って客観的に思えて、それだけでちょっと心に余裕ができるかもしれません。
そして、安心した分、ちょっと力が抜けやすくなるかもしれませんね!
力を抜くって、実は自然なことなんです
香庵ではS様からの「噛みしめ治療」のご依頼でも、全身のバランスやおからだの状態をチェックしていきます。
その時に「結構、肩のコリも今日は強めですね~」とか、「背中から腰全体も施術ベッドから浮き上がって無意識でブリッジしてる姿勢だからゆっくり眠れなかったりしませんか?」など、S様とおからだの状態を共有していきます。
からだに現れた症状って、実はほんの一部。
もともと、筋肉の疲労や気の使い過ぎ、睡眠不足など、なにかでエネルギーを消耗して元気がチャージされなくなり、からだの歪(ひず)みが「症状」として現れているケースがほとんどなのです。
だから「1ヶ所だけが悪くて、他の場所はぜーんぶ問題なし!!!その場所だけ治せばいい!」っていうふうには、東洋医学では考えないんですね。
このような鍼灸治療の基本的な考え方があるので、S様との鍼灸治療でも、どこをどんなふうにゆるめながら「噛みしめ治療」と関連付けていくかをお話しています。
こうした鍼灸治療の流れがベースにあるので、S様も自然と症状を1つだけしか言っちゃいけない、って思わなくていいんだ~!って感じてくださったようです。ずっと前にお母さまから指摘され気にされていらしたことも自然な流れでお話してくださいました(*´▽`*)
力を抜くために知っておきたい、たった1つのルール
今回は鍼灸治療で症状改善もできたのですが、この状態をキープしながら、S様ご自身でも左右の肩の高さを整えられるようなセルフケアがあると安心感がアップするのではないか、というご提案をさせていただきました。
普段、セルフケアもされていらっしゃるS様だからこそ、そのついでにできそうなワークがいいのではないかなぁ(^^♪ということで、
肩まわりを脱力してほぐすストレッチと体操を組み合わせたワークをご紹介しました。
でも、「さぁ、ワークだ!力を抜こう!(* ̄0 ̄)/ 」って思った瞬間・・・
逆に「力を抜かなくちゃ・・・!結果を出さなくちゃいけないんだ・・・!(>_<)」って緊張されてしまって、肩周りの筋肉全体が緊張するクセが現れてチカラを抜くのが難しそうでした。
ご本人も「昔から、力を抜くのが苦手なんです…」とちょっと自信なさげにおっしゃいます。
でも大丈夫!(^ω^)実は、力を抜くのって、あるルールがあるんです。そのルールを知ってから再びワークに取り組んでいただくと、あら不思議♪
肩から腕、指先までがブラ〜ンブラ〜ンと脱力できてるではないですか♪( ^ω^ )
S様も「あれ…?力、抜けてますね~(//∇//)」とちょっとびっくりされながらも嬉しそう♪
それを眺めている私も嬉しくなりました(^ω^)v
S様にご紹介したワークは力を抜く感覚を養う基本的なエッセンスがぎゅぎゅっと詰め込まれていて、やり方はシンプルですが、肩コリをほぐす効果が高いので私も愛用しているお気に入りの方法のひとつなんです(^^♪
朝の目覚めをスッキリと!
お仕事の合間のリフレッシュに♪
夜寝る前のリラックスタイムに★
いつでもどこでも、時間も場所も取らないカンタン・ワーク。
S様、ぜひ気が向いたときにでもご活用くださいね!
力を抜くことができると、からだは変わる
力を抜くって、リラックスした状態には欠かせませんよね(o^―^o)
逆に、コリや痛みがあると力が抜きにくくなってきます。
これは香庵に来院されたことのある方は「あぁ、鍼灸治療前のあのチェックで言ってるアレのことだな~( ̄▽ ̄)」ってピーンとくるかもしれませんね(笑)
チカラを抜くワークを知っておくと、普段のセルフケアの効果を高められたり、疲労感を早く取ることができたり、鍼灸治療の効果を長続きさせたりなどなど、いろいろな利点があるんですよ~!
ご興味のある方は施術後にご紹介しますね!
お気軽にお声がけくださいね。
五反田の鍼灸院 香庵(かのん)
東京都品川区大崎5-4-7ハイツ五反田203号
五反田駅をご利用の方
JR山手線・都営浅草線 五反田駅西口改札 徒歩5~7分(約500m)